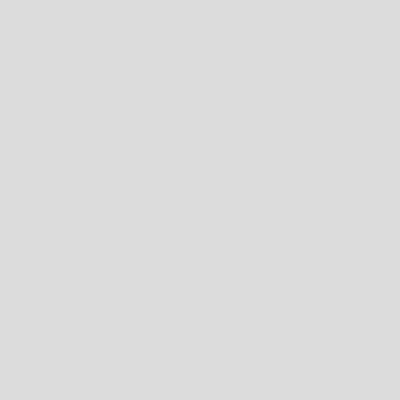城島の酒
日本有数の酒処・久留米城島町で学ぶ。
時代とともに流れる、馥郁(ふくいく)たる日本酒のストーリー

城島の酒蔵のなかでも最も古く歴史のある「花の露」。屋根が低く、敷地を贅沢に使った平らな建物は城島の酒蔵の特徴でもある
のんびりと流れる筑後川沿いに点在する煙突と白壁の蔵。久留米市の城島町と三潴町、大川市にかけての一帯は、「日本有数の酒どころ」として名高い地域です。現在も久留米市と大川市合わせて16の酒蔵が残り、そのうち城島町を中心とした8蔵が参加する毎年2月の「城島酒蔵びらき」では2日間で約11万人もの人でにぎわいます。

西島伊三雄に描かれた江戸時代の酒造りの様子。いつかこの絵のように、昔ながらの酒造りをするのが冨安さんの夢。

13代目の冨安拓良さん
気候風土と杜氏の情熱が育てた城島の酒造り
まずは、城島の酒造りの歴史を紐解くため、城島で一番古い酒蔵「花の露」13代目の冨安拓良さんを訪ねました。「一番古い記録によると、城島で酒造りが始まったのは江戸時代中期の延享2年(1745年)とされています。筑後川の軟水と肥沃な筑紫平野の米、それに脊振山の北風による冬の冷え込みにより、きめが細かく香りの良い日本酒ができたそうです」。また、筑後川では船による輸送ができ、筑後川上流にある酒に深い薫りをもたらす木樽の原料となる日田杉が手に入ることも発展を支えたのだと教えてくれました。

「花の露」の蔵の2階には、江戸や明治、大正の酒造りの道具や写真が展示された資料館がある。

酒蔵の中に残る木樽。今でも現役で使われている
順風満帆なように思われた酒造りでしたが、明治に入って全国に販路を広げた時先に全国で飲まれていた「灘の酒」との質の差に愕然とします。醸造方法を研究し、機械を改良、ついには灘から杜氏を招いて試行錯誤を繰り返しますがなかなかうまくいきません。実は、硬水である灘の水に比べ、城島の水は軟水だったため、灘の手法ではうまく仕込めなかったのです。ようやく原因が判明してからも、手探りでの改良は続きました。
そして、幾度もの挑戦の末生まれたのが、城島の軟水を生かした「すずやかでやさしい口当たりの酒」です。それは、硬水を使った灘とはまた違う、新たな味の可能性を広げた酒として品評会でも評価されました。ついに「東の灘、西の城島」として、肩を並べるようになったのです。
時代に合わせた味造りとイベントで日本酒業界を活性化
明治も後期になると日本酒は軍需物資としても重宝され、全国で酒蔵が次々と創業。城島でも最盛期には80以上の蔵があったそうです。しかし、昭和に入ってからは日本の生活様式が変わり、洋食にも合うビールのシェアが急増し、アルコール度数が高く、肴を選ぶ日本酒は徐々に消費量が少なくなり、それに伴って酒蔵の数も減っていったのです。
そんな現状を変えるべく、城島では低アルコールでも日本酒らしい深みを残した銘柄やスパークリング日本酒など、それぞれの蔵で新たな商品の開発を進めています。さらに酒蔵の若手経営者同士や商工会での情報共有も積極的に実施。その中で生まれたのが、半径10km以内に酒蔵が集中する城島地区の特性を生かして、各蔵の新酒を飲み歩く催し「城島酒蔵びらき」です。1994年の発足当初は一日だけの開催でしたが、徐々に集客が増え、一日に7万人もの人で賑わうビッグイベントへと成長しました。今では二日間で10万人以上が押し寄せ、いつもは普通電車しか停車しない「三瀦駅」に、この日だけは特急電車が止まります。グルメやステージなども開催されるので、今まで日本酒に親しみのなかったファミリー層や若い世代にも楽しまれています。
実は、この酒蔵びらきの運営も酒蔵の大事な役割。地元と一丸となっての取り組むことで、かつてのにぎわいを少しずつ取り戻しているようです。

「花の露」は日本で初めて屋外ステンレスタンクを開発した酒蔵でもある
城島の未来を握るのは、蔵の個性が彩る唯一無二の味わい
他の酒どころとの差別化も課題の一つ。冨安拓良さんによると「酒造りには正解が無いんですよ。現在では品評会で評価の高い味を目指しても、上位になるにつれ、個性が消えてしまいます。しかも機械や運送技術が進んだ分、地域差もどんどん曖昧になっている。競合との差別化には、地元の気候風土を生かした味、蔵の個性をもっと出していかないと」

タンクの中でプツプツと音を立て発酵する原酒。甘酸っぱい香りが芳醇な味わいを予感させる
実際に「花の露」では、酵母と雑菌を排除する人工的な乳酸を使わず、蔵に住み着いた菌で作る「生酛(きもと)」と呼ばれるお酒にも力を入れています。これは江戸〜明治時代に主流とされてきた作り方で、仕込みの工程には手間がかかりますが、甘みも酸味も強く、複雑な風味になるのだとか。まさに蔵の個性を表す味です。
活性化しつつあるといっても、酒蔵にとってはまだまだ厳しい状況が続いていますが、実は今こそ日本酒の夜明け前。一年で最も寒い時期に旨みを蓄える新酒のように、酒どころ・城島が紡いできたブランドが今からどんな味を咲かせるか、ますます目が離せません。

「花の露」は古い謡曲で唄われた「命を長らえる高貴薬」とも、中国語で酒を表す雅語とも言われている
[INFORMATION]
■城島酒蔵びらき
2019年2月16日(土)−17日(日)
詳しい情報はこちら▽
http://nanbu-shoko.jp/sakagura/